
※本記事には、アフィリエイト広告を含むプロモーションが掲載されています。
こどもの「イヤイヤ期」はどうして起こる?
こどものイヤイヤ期は、成長の一環として誰もが通る道です。
特に2〜3歳頃は自己主張が強くなり、「なんでも自分でやりたい!」「思い通りにならないと嫌!」という気持ちが爆発しやすい時期です。
しかし、親としては毎日のように「イヤ!」と言われるとストレスを感じてしまうこともありますよね…。
時間がないときや急いでいるときに限ってイヤイヤが始まり、どう対応すればよいか悩んでしまうことも少なくありません。
そんな時に大切なのが、こどもが素直に受け入れやすい「楽しい声かけ」です。
声のかけ方ひとつで、イヤイヤがスムーズに収まり、親子のコミュニケーションがより楽しくなります。
この記事では、こどものイヤイヤを減らすための具体的な声かけ例や実践テクニックを紹介します。
毎日の育児が少しでも楽になるよう、ぜひ試してみてください♪
イヤイヤを減らすための基本ポイント
こどものイヤイヤに対処するためには、いくつかの基本的なポイントを押さえておくことが大切です。
イヤイヤ期は成長の一部とはいえ、毎日続くと親も疲れてしまいますよね。
しかし、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、こどもが自ら進んで行動しやすくなり、イヤイヤが減ることがあります。
重要なのは、こどもの気持ちを尊重しつつ、楽しく促すことです。
ここでは、親がすぐに実践できる具体的なポイントを紹介します。
育児の負担を減らし、親子の時間をより楽しいものにしていきましょう!
こどもの気持ちを受け止める
まず大切なのは、こどもが「イヤ!」と言ったときにすぐに否定しないことです。
こどもは「ダメ!」や「そんなこと言わないの!」と否定されると、余計に反発しやすくなります。
こどもがイヤイヤするのは、「自分の気持ちを分かってもらいたい」というサインです。
たとえ親にとっては些細なことでも、こどもにとっては大切な気持ちが詰まっています。
「そっか、○○がしたかったんだね」「嫌だったんだね」と気持ちを言葉にしてあげるだけで、こどもは安心しやすくなります。
また、共感の言葉を添えることで、こどもは「ちゃんと分かってもらえた」と感じ、落ち着きやすくなります。まずはこどもの気持ちをしっかり受け止めることを意識しましょう。

わたしも子どもたちのイヤイヤに対して「そうなの~○○イヤなの?」とイヤな気持ちに寄り添う言葉かけをするようにしています!
効果があるのか、高確率でとりあえず泣き止みます👍
選択肢を与える
こどもは「○○しなさい!」と指示されると、自分の意思が無視されたと感じて反発しやすくなります。
特にイヤイヤ期のこどもは、「自分で決めたい!」という気持ちが強いため、一方的に命令すると「イヤ!」と拒否しがちです。
そこで有効なのが、こどもに選択肢を与えることです。
「青い服と赤い服、どっちを着る?」「靴は右足から履く?左足から履く?」と選ばせることで、こども自身が決定権を持ち、自発的に行動しやすくなります。
また、「お風呂に入る?それともパパと遊んでから入る?」といったように、どちらを選んでも目的の行動につながる選択肢を用意すると、スムーズに進みやすくなります。
こどもが「自分で決めた!」と思える工夫を取り入れることがポイントです。



さっきの流れで「そうなの~○○イヤなの?じゃぁ□□と■■どっちにする?」と聞くと泣き止んで、しばらく考えた後、「■■」と選んでくれます!
我が家でよく使うパターンは「(寝るのイヤがる時)パパとママ、どっちとねんねする?」「(おやつを食べたのにもっと欲しがる時)今おやつをもう1つ食べて夜ご飯食べないか、明日おやつ食べて夜ご飯も食べるか選んで?」など、イヤイヤ・わがまま発動するときは、2択かつ選んで欲しい結果につながる質問をするよう意識しています!
遊び感覚を取り入れる
こどもは「やらなきゃいけないこと」を強制されると、「イヤ!」と拒否しやすくなります。
そんな時に有効なのが、遊びの要素を取り入れて、楽しく行動できるようにすることです。
例えば、「歯磨きしよう」と言うだけではなく、「歯ブラシさんが、○○ちゃんの歯をピカピカにしたいって!」とキャラクターを使った声かけをすると、こどもはワクワクしながら歯磨きに取り組めます。
また、「片付けしよう」ではなく、「おもちゃさんが『おうちに帰りたいよ〜!』って言ってるよ!」と言うと、こどもは自然と片付けを始めます。
「遊びながらやる」という工夫をするだけで、イヤイヤがぐっと減り、こどもが積極的に行動できるようになります。



小芝居めっちゃ取り入れています!
4歳長男には最近あんまり効きませんが、3歳次男にはまだ効果的です👍
「あっ、次男君のお口の中に虫歯キンマンがいる!!ママが歯ブラシまんからもらった歯ブラシでやっつけてあげるよ✨」みたいな感じで言いながら磨いています♪
親子でできる楽しい声かけ例
こどものイヤイヤを和らげるためには、「やらなければならないこと」を「やりたいこと」に変える工夫が大切です。
そのためには、こどもが楽しくなるような声かけを意識するだけで、スムーズに行動しやすくなります。
例えば、「早く着替えて!」と命令するのではなく、「今日はどっちの服を選ぶ?」と選択肢を与えるだけでも、こどもの気持ちは変わります。
また、「おもちゃを片付けなさい!」ではなく、「おもちゃさんがおうちに帰りたがってるよ!」と言うと、こどもは楽しんで片付けを始めます。
日常の声かけを少し工夫するだけで、イヤイヤが減り、親子のコミュニケーションもより楽しくなります。
次の章では、具体的な声かけの例を紹介します。
着替えを嫌がるとき
❌「早く着替えて!」
⭕「今日はどっちのお洋服にする?こっちにする?それともこっち?」
こどもは「自分で決めたい!」という気持ちが強いため、一方的に指示されると反発しやすくなります。
そんなときは、選択肢を与えて「自分で選んだ」という満足感を持たせることがポイントです。
また、「このお洋服さん、○○ちゃんに着てもらいたいって!」とキャラクター設定をすると、より楽しく着替えやすくなります。
遊びの要素を取り入れることで、自然と着替えを促すことができます。
野菜を食べたくないとき
❌「野菜を食べないと大きくなれないよ!」
⭕「このお野菜を食べると、○○レンジャー(好きなキャラクター)みたいに強くなれるよ!」
こどもは「嫌なことを押し付けられる」と感じると、ますます拒否したくなります。
しかし、ヒーローや憧れのキャラクターと関連づけると、「食べたい!」という気持ちが生まれやすくなります。
また、「このニンジンを食べると、足が速くなるんだって!」「ほうれん草を食べると、力持ちになれるよ!」と具体的な効果を伝えると、さらに興味を持ちやすくなります。
楽しみながら食事ができるよう、工夫してみましょう!
お風呂に入りたくないとき
❌「早くお風呂に入らないと風邪ひくよ!」
⭕「今日はお風呂にワニさんがいるかも!?探しに行こう!」
こどもは「やりなさい!」と言われると反発しやすいですが、ワクワクする要素を加えると、自分から行動しやすくなります。
例えば、「お風呂にバイキンが隠れてるよ!お湯で流しちゃおう!」や「アヒルさんたちが○○ちゃんを待ってるよ!」など、こどもの想像力を刺激する声かけをするのがポイントです。
また、お気に入りのおもちゃを使ったり、「泡アート」を楽しんだりすると、お風呂の時間が楽しいものになり、自然と入りたくなるようになります。
出かける準備をしたくないとき
❌「遅れるから早くして!」
⭕「よーし!ママとどっちが早く靴を履けるかな?よーいドン!」
こどもは「急いで!」と言われると、余計にのんびりしたくなることがあります。
そこで、競争形式にすることで、遊び感覚で楽しく準備ができるようになります。
また、「靴さんが○○ちゃんに履いてほしいって!どっちの足が先に入るかな?」や「玄関までカニさん歩きで行こう!」など、こどもがワクワクする要素を加えると、自然と準備が進みやすくなります。
楽しい雰囲気を作ることがポイントです!
ご飯を食べたくないとき
❌「残さず食べないとダメでしょ!」
⭕「このスプーンで、お口にポン!○○電車がトンネルに入りまーす!」
こどもは「食べなさい!」と命令されると、逆に食べたくなくなることがあります。
そんなときは、遊びの要素を取り入れることで、楽しく食事ができるようになります。
例えば、「飛行機が離陸しまーす!着陸先は○○ちゃんのお口です!」や「スプーンさんが○○ちゃんのお口に行きたがってるよ!」など、こどもがワクワクする演出を加えるのがポイントです。
食事の時間を楽しいものにすることで、自然と食べる意欲が湧いてきます!
トイレに行きたくないとき
❌「トイレに行かないとお漏らししちゃうよ!」
⭕「トイレに行くと、バイキンさんがびっくりして逃げちゃうんだって!やってみよう!」
こどもは「トイレに行きなさい!」と指示されると、反発して行きたがらないことがあります。
そこで、ゲーム感覚で楽しく誘うと、自分から行きたくなることが増えます。
例えば、「トイレで水を流すとバイキンさんが『キャー!』って逃げちゃうよ!」や「トイレの神様に会いに行こう!」など、ワクワクするストーリーを作るのがポイントです。
楽しいイメージを持たせることで、トイレ習慣が身につきやすくなります!
病院や歯医者に行きたくないとき
❌「泣いても行くんだからね!」
⭕「今日は○○先生と会える日だよ!先生に元気な○○くん(ちゃん)を見せに行こう!」
こどもは病院や歯医者を「怖い場所」「痛いことをされる場所」と思うと、ますます行きたくなくなります。
そこで、「先生に会いに行く」とポジティブなイメージに変えると、安心して向かいやすくなります。
また、「終わったらシールをもらえるかも!」「診察が終わったら、ママとごほうびのお散歩しよう!」など、
行くことのメリットを伝えると、前向きな気持ちになりやすくなります。
リラックスした雰囲気で声をかけるのも大切です!
手をつなぎたくないとき(外出時)
❌「手をつながないと危ないよ!」
⭕「手をつないでパワーを送ると、ママ(パパ)と○○パワーが出るんだよ!やってみる?」
こどもは「危ないから!」と注意されると、逆に反発してしまうことがあります。
しかし、手をつなぐことに特別な意味を持たせると、自然と受け入れやすくなります。
例えば、「手をつなぐと魔法が使えるよ!」「パワーがたまるとジャンプできるかも!」とゲーム感覚を取り入れると、楽しく手をつなげるようになります。
親子で笑顔になれる声かけを工夫してみましょう!
お片付けをしないとき
❌「おもちゃを片付けなさい!」
⭕「おもちゃさん、おうちに帰りたがってるよ!どこに帰るのかな?」
こどもは「片付けなさい!」と命令されると、面倒に感じてしまい、なかなか動こうとしません。
しかし、おもちゃをキャラクター化すると、「おもちゃを助けてあげよう!」という気持ちが芽生え、楽しみながら片付けができるようになります。
例えば、「ぬいぐるみさんはお布団で寝たいんだって!」「積み木さんたち、並んでおうちに帰るんだって!」とストーリーを作ると、さらに興味を持って取り組めます。
遊び感覚で片付けができる工夫をしてみましょう!



お子さんに合った言い回しがきっと見つかる!
少しでもイヤイヤは子どもの成長!
そんな成長をママも楽しみながら見守りたいですね♪
イヤイヤがひどいときの対処法
こどもがどんなにイヤイヤをしても、親が冷静に対処することが最も大切です。
イヤイヤがひどいときは、感情的にならず、一度深呼吸して落ち着きましょう
こどもは「自分の気持ちを分かってほしい」「思い通りにしたい」という思いからイヤイヤをします。
そんなときは、まずこどもの気持ちを受け止め、共感することがポイントです。
また、無理に行動を押し付けず、「○○が終わったらやってみようか」など、少し時間をおいて声をかけると、こどもも気持ちを切り替えやすくなります。
焦らず、こどものペースを大切にしながら対応することが重要です。
無理に押し通さない
こどもが「イヤ!」と言ったとき、無理やりやらせようとすると、さらに反発が強くなり、イヤイヤが激しくなることがあります。
特にイヤイヤ期のこどもは、「自分で決めたい!」という気持ちが強いため、強制されると余計に拒否したくなります。
そんなときは、こどもの気持ちに寄り添いながら、楽しい雰囲気を作ることがポイントです。
「○○したら一緒に△△しよう!」と楽しみをセットにしたり、「どっちからやる?」と選択肢を与えると、自然と受け入れやすくなります。
こどもが自分で動きたくなる工夫を意識しましょう。
一度、こどもから離れてみる
こどもが強くイヤイヤをしていると、親もつい感情的になってしまい、イライラしてしまうことがあります。
そんなときは、無理に言い聞かせようとせず、一度深呼吸をして、こどもから少し距離を取ることが大切です。
たとえば、別の部屋に移動したり、窓の外を眺めたりして気持ちをリセットすると、冷静に対応しやすくなります。
親が落ち着くことで、こどもも次第に気持ちを切り替えやすくなります。
無理に対処しようとせず、「少し時間をおいてから話そう」と考えるだけでも、心に余裕が生まれます。
イヤイヤが続くときはルーチン化を
こどもは先の見通しがつかないと不安を感じやすく、イヤイヤにつながることがあります。
そんなときは、毎日の行動をルーチン化することで、自然と習慣になり、イヤイヤが減りやすくなります。
例えば、「ご飯の前に手を洗う」「寝る前に絵本を読む」「お風呂の後はパジャマを着る」といった流れを決めておくと、こどもも「次はこれをするんだ!」と理解しやすくなります。
ルーチンが身につくと、こども自身が自発的に動きやすくなるので、親の負担も軽減されます。
まとめ
こどものイヤイヤは「自分でやりたい!」「思い通りにしたい!」という成長の証ですが、親にとっては大変な時期でもあります。
特に忙しいときや急いでいるときにイヤイヤが始まると、ついイライラしてしまうこともありますよね。
しかし、ちょっとした声かけの工夫をするだけで、こどものイヤイヤが和らぎ、親子のコミュニケーションがスムーズになります。
- こどもの気持ちを受け止める(まずは共感し、安心させる)
- 選択肢を与える(こども自身に決めさせることで自発的に行動しやすくなる)
- 遊び感覚を取り入れる(楽しさをプラスすることで、自然と行動につなげる)
この3つを意識しながら、親子で楽しい声かけを取り入れてみてください。
毎日の育児が少しでも楽になり、こどもとの笑顔の時間が増えることを願っています♪
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
※本記事には、アフィリエイト広告を含むプロモーションが掲載されています。安心してご利用いただけるよう、誠実な情報提供を心がけています。










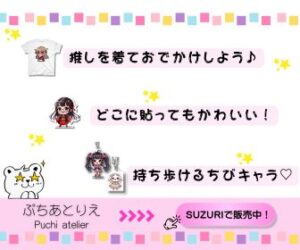
コメント